演出・振付 マシュー・ボーン
於 シアター・コクーン
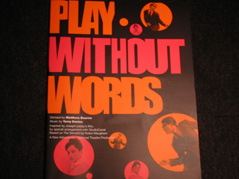
それは、そういうもの。
2004年7月『PLAY WITHOUT WORDS』
演出・振付 マシュー・ボーン
於 シアター・コクーン
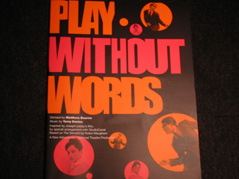
「とにかく、僕にとってもっとも魅力的なのは60年代前半までの(イギリスの)映画
だった・・・」マシュー・ボーンは、言う。50年代までつづいていた抑圧的な政策の影
に、ひとびとはまだすこしとらわれていたが、それでいて、新しい時代へむけてたしか
に動き出そうとしていた。そんな、大きな変革が起きるちょっと前の時代の映画には、
なにやら「言ってることとやってることがバラバラ」なような、なんとも言えないような、
ふしぎな感じがあったようである。これが、21世紀の振付家で演出家のマシュ―・
ボーンを、つよくひきつけるというわけである。
舞台『PLAY WITHOUT WORDS』には、タイトルからしてわかるように、
まったくセリフはない。でも、しっかりとしたドラマはある。青年貴族の家に、ひとりの
召使とメイドがやってくる。青年貴族は、メイドと恋におちる。彼のフィアンセもまた、
召使の友人と危険な関係におちる。結局、青年貴族は、破滅する。すべては、
召使のしかけた罠だったのである・・・。こんなドラマが、とにかく徹底的にダンスで
語られる。ジョセフ・ロージー監督、ハロルド・ピンター脚本の映画「召使」(63)が、
ステージ化されている。ほかにも、マシュー・ボーンが愛するいくつものイギリス映画の
きらめきで、ステージはいっぱい!
ひとりの登場人物を、同時に異なった3人のダンサーが演じる。舞台にはまったく
同じ服装のダンサーがひとりの人物につきいつも3人ずつ出てきて、ちょっとずつ
ちがったふうに動く。みている方は、はじめはだれをみたらよいのか迷ってしまう。
なんだか目もチカチカしてくる。しかし、ふしぎなもので、やがて、登場人物のあたま
のなかの思考のプロセスにぐっと入りこんでいくような気分になってくる。
こんなふうに、ひとつの役を何人かが同時に演じるやり方自体は、このところ
よくみられるかもしれない。たとえば、マシュー・ボーンと同じイギリスの演出家
サイモン・マクバーニーの『エレファント・バニッシュ』(世田谷パブリックシアター)
なんかも、そう。昨年にひきつづき今年再演されたこの作品は、村上春樹の
いくつかの短編を合わせてステージ化したもので、文学性・思索性のつよい
舞台作品であるところがなかなかよい。これにくらべると、『PLAY WITHOUT
WORDS』は、ポピュラーでたのしいエンターテイメント風。どちらにしても、
大人っぽい良質な作品である。
といっても、すこし前だったら、こんな分裂症的な演出は、たんに自意識過剰なだけ
のへんてこな人物の考えつくものととらえられたかもしれない・・・?『PLAY
WITHOUT WORDS』は、官能的な舞台である。といわれているが、結局、
私たちにとってまったくふつうじゃないアナザー・ワールドを、一見ふつうに
わかりやすく、ステキにみせてくれている舞台といえるかもしれない。そこで、
実は、マシュー・ボーンのあたまのなかでは、「言ってることとやってることが
バラバラ」なような「変革の時代」が、今もずっとつづいている・・・そう考えると、
おもしろくなってくる。
マシュー・ボーンのような、ダンスと演劇をつなぐタイプの演出家の「ステージングの
妙」といったものをみていると、いくつかのアイディアの「つなぎ方」について考えて
みたくなる。彼の場合、たいてい、一般によく知られたストーリーとかドラマがまず先
にあって、それを彼なりに解釈したいという欲望の中から、たくさんのアイディアが
生まれてくるのかもしれない。また、あるいは、もともと彼がもっていたアイディアを
ドラマに託して生かすということもあるだろう。だから、マシュー・ボーンのステージング
は、いくつかのアイディアを「つなぐ」というより、大きく「つつむ」のだといった方が
いいかもしれない。
これに対して、文字どおりアイディアをドラマで「つなぐ」といった感じの舞台といえば、
あのピナ・バウシュのタンツ・テアターもそのひとつじゃないかと思う。彼女のダンスの
アイディアは、はじめは、むきだしだったり、逆にすごく親密だったりするものと思わ
れる。そんなアイディアは、手づくりのドラマのラインでゆるやかにつながれていくよう
である。タンツ・テアターの名には、30年のときが刻まれている。日本をテーマにした
7月公演新作『天地』(彩の国さいたま芸術劇場)では、どこかつじつまの合わない
ような、あのピナ・バウシュらしい「女性の語り」とダンスが、今回はある種の絶対的
なしずけさとともに組み合わせられている。ドラマの構築性からも、ダンスの雄弁さ
からも、すこしはなれたポイントを、今の彼女はじっとみつめているのだとわかる。
(マシュー・ボーンとピナ・バウシュでは、ボーンのダンスのほうがやや古典的な
制約のもとにあるといえる。そのぶん、ドラマやスタイルのみせ方が大きくなって
いるとも考えられる。)


私が思うに、アイディアを「つなぐ」舞台と「つつむ」舞台は、両方とも、「精神的な闇」
とよべるようなものをとり込みやすいのである。これは、大きなストーリーやわかり
やすいことばが示す、コンセプトとしての「人生の闇」とはちがう。これは、実際に
舞台をみている私たちを、あらゆる記憶の外に連れていく。そして、そこに私たちを
しばらくのあいだ拘束する。それだけ、多様で深刻なものだったりする。それでいて、
そんな「つなぐ」「つつむ」系の舞台の「闇」は、いつもどこかで「たのしさ」とつよくむすび
ついている。いくつものアイディアが視覚的に再構成される過程で、思考と思考の
あいだの「闇」がバージョンアップされるのだろう。(これこそ、めくるめくステージング
の魔力?)そして、たぶん、私たちが舞台をしっかり「観た」というきもちになるときは、
この「たのしさ」の感覚を、演出家のシステマティックな思考のたまものであると
自然に感じているのではないかと思うのである。
『PLAY WITHOUT WORDS』でいえば、マシュー・ボーンは、「ことばがなくても、
きもちは伝わる」式のことをやってみせたかっただけじゃないという気がする。私は、
この舞台をみるまえから、もともと、ダンスの舞台はセリフのある演劇よりもたくさんの
はっきりしたことばを発するものと思っている。「ことばがなくても、きもちは伝わる」式
というよりは、「からだのことばで伝える」式の舞台をみることは多い。それより、
「言ってることとやってることがバラバラ」なような感覚を、ほんとうにダンスだけで
みせることは、もしかするとムリなのではないかとも私は考えている。(ひとが、
ひとつの生命体であるかぎり・・・というイミで。)そんなムリなことに挑戦しようと
するマシュー・ボーンのあたまのなかには、一体どんなシステムができあがって
いるのだろう・・・?たとえそれが、どんなものであっても、私は「それは、
そういうもの」というふうに、まるごとシンプルに受けとめるしかない・・・こう感じる
とき、私の目は舞台のために、もう一度パッとみひらかれるのである。
ところで、マシュー・ボーンは、ひとつの役を2人ではなく、3人に分けるところが
おもしろいのだと言っているけれど、そうなのかな─?と私は思う。この舞台でいちばん
セクシュアルでスリリングな、青年貴族とメイドの恋のダンスだけはそれぞれ
2人ずつになっている。ここで、同じ服装のカップルがもう一組いては、やはり
散漫な感じになってしまっていたにちがいない。ときには2人もいいんじゃないか
ということではなく、2人と3人の組み合わせが大切なのかもしれない。
そうすると、舞台をみる私たちのあたまは、これからもっとスピーディーな
情報学的転回を求められていくことになるのであろうか?これはちょっと
むずかしそうなので、今はあまり気にしないでおこう・・・と思う。