

ニノ ニナ


ニノ ニナ
おはなしのおわりに、今までつづいてきたながい時間を、一発で粉々に、上手にふっとばして
みせてくれるオソロシイもの・・・といえば、ピストルである。このところ、私がみる岩松の舞台に
は、ピストルがよく出てくる。
一昨年の『「三人姉妹」を追放されしトゥーゼンバフの物語』でも、昨年の『西へゆく女』でも、
登場人物が大団円でピストルをとり出す。今年の『ワニを素手でつかまえる方法』には、
ピストルがでない。そのかわりにワニがいる。『シブヤから遠く離れて』では、またもやピストルが
鳴る。こちらには、ふだんはピストルとはミスマッチの感じの「ニノ」ことニ宮和也もいる。舞台の
ニノは、TVのニノとはまたちょっと違う。「ニナ」(?)こと蜷川幸雄の目が光っている・・・。
『ワニを素手でつかまえる方法』は、「第4回タ・マニネ公演」。小林薫が主宰する岩松了との
コラボレーョン的 シリーズである。個性的な俳優陣がそろって、かるいようなおもたいような
岩松世界をさらりとみせる感じがよいと思う。
片桐はいり演じる女のひとり語りから、この舞台の幕があく。
そうよ、ここが私のふるさとだわ・・・好きよ、だって嫌いになる理由がないもの・・・例えばどんな?・・・(笑って)
私がそんな女に見える?こわいわ、喫いガラでいっぱいの灰皿みたい・・・捨てろと怒られそうなの、「待て待て、
思考はつづいてる!」とか、フフフ・・・だからお願い、もう考えないで・・・このままの私を見て・・・感謝してる、
あなたに会えたこと・・・いつも思ってた、ここらへんに(と頭上を)神様がいるんだなあって・・・ホントよ・・・ううん、
そういうんじゃないけど、でもそうしか言えないのよ、カミサマって・・・(手をさし出して)・・・握手・・・ね、・・・
そして、さよなら・・・私は残るわ・・・これからは、そうね・・・ただ季節を感じる、あなたのかわりに・・・だって、
これまではあなたが私の季節だったから。
こんなちょっと「かっこいい」セリフから、たちまち「めちゃくちゃ」なドラマがはじまっていく。女の名は、
うさぎ。うさぎは、若い息子をもつ娼婦である。ところは、港町のふるいホテル。ホテルの時計は、
泊り客が船の出発時刻に遅れないように、いつもわざと5分だけ進めてある。いってみれば、
「善意のホテル」なのである。このホテルで今、暴力団によってワニの密売が行われようとしている。
そして、組長は、組員のひとりとホテルの亡支配人の娘を結婚させようと している。ワニが逃げだす。
小林薫演じるフレディと名のる男が、久しぶりに呼ばれる。流しの歌手でありながら、ワニの捕獲員の
資格をもつフレディがワニをみごとに捕える。ところが、そのころ、組員の右手は、さまざまな苦悩の
なかでだんだん不気味に変形していく。ついにある日、組員の指のあいだにみどりの水かきが
はっきり現れて・・・ そして全身が・・・。
舞台のさいご、うさぎは見えない存在(神?)から見えないたべものをもらって、それを大事にすこしずつ
たべる。トイレに行こうとするうさぎに、ホテルの娘がしずかに声をかける。「暗いわよ。」すると、
「のぞむところよ。」うさぎはきっぱりと言う。 彼女は今までになく毅然としてトイレに向かって進んでいく。
ここで客席からは、「はは・・・」と脱力系の笑いがおきる。 けれど、これはちゃんと「こわい」おはなしである
こともわかるようになっている。ラストのラスト、だれもいなくなった舞台 のフロアーを、巨大なみどりの
ワニが、ゆっくり這っていく。人間そっくりに、かなしく、這っていく・・・。
結局、ピストルが出てこない岩松の舞台は、なんとも「きもちわるい」ことになるのである。ドラマは、
生と死の混沌の局面である。とすれば、劇作家が此岸と彼岸をむすんでみせるとき、ピストルはひとつの
美学になる。ピストルは、ほんとうに一発でストーリーを消してしまう。それと同時に、作者自身も消して
しまう。バン!という音といっしょに、私たちのゆめと現実がぐるぐるまざりあう。それは、客席という闇の
中の一瞬のできごと。でも、ピストルがないと、明るい舞台の上で、どうしても人間が人間でない、
なんだかわからないようなかたちをとらざるをえなくなってしまうこともある。 これもまた、あるイミで
究極のドラマである。
ところで、人間が人間のかたちをじょじょに失い、別の生物と化していく──そんなタイプのおはなしは、
たいてい、 「なまなましい」あるいは「ナンセンス」なんていわれることが多いかもしれない。私たちは、
こんな言いまわしをとおして、 日常的な視点からみて一見違和感のある状態に一定の評価をあたえようと
しているともいえる。最近では、こんなことば がほめことばとして使われるのもよく耳にする。ただ
『ワニを〜』は、「なまなましい」というよりは、やはり「きもちわるい」と いいたくなる。(あいをこめて・・・)
これは、どちらかといえばドライなコメディタッチの作品といえるけれど、「ナンセンス」というだけでは
足りないような気がする・・・。
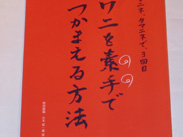
「なまなましい」あるいは「ナンセンス」というような感覚は、実は「テクスト中心」の考えのほうから
やってくるものなの ではないだろうか。もっとも、「なまなましい」と「ナンセンス」は、違う意味の
ことばでもある。同じことが違うことばであらわされるとき、そこにすでに価値のシフトが生じて
いるともいえる。ただ、それはあくまでも「テクスト」の側のできごとではないだろうか。けれども、私はこの
岩松の舞台を、「テクスト」の側からではなく、どうしても「ただの観客」「ただの人間」の側からみてしまう
のである。といっても、作品をヒューマニスティックな立場から解釈したいということではない。私が
客席で胸に抱くこと、それは、実は、「なまなましい」とか「ナンセンス」とか・・・そんなことばの価値の
システムを構成するヨウソを、ちょっと並べかえてみたい・・・なんていうようなひそかな(おかしな)欲望で
あったりもする。
『テクストから遠く離れて』で、加藤典洋氏は、テクストと作者をまったく切り離して考える「テクスト論」の
限界を、近年に書かれたいくつかの日本語の小説と、バルト、デリダ、フーコーの思想と比較して
説いている。つまり、ここ 30年来、「テクスト」のむこうにある実体としての「作者」は、「テクスト」の中の
「書き手」と「読み手」の両方の側から 否定されてきた。けれども、そのような考え方をしていくうちに、
人は「テクスト」から「意味」を受けとることができなくなってしまっていると、加藤氏は主張する。
( たとえば、水村美苗の『続明暗』。水村は、漱石の未完の小説『明暗』を、意識して「テクスト中心の
読み方」で 読み解いたというようなことを述べている。と同時に、漱石の文学的意図からは離れて、
「ただの読者」として物語のつづきに思いをはせたというようなことも言っている。ここに、加藤はひとつの
矛盾をみる。つまり、水村は、「ただの読者」と「書き手」の両方であることから、『続明暗』を書き
はじめている。ということは、水村は、あえて「作者」としての自分を消していることになる。そうする
ことで、もう一度あたらしい「作者」としての自分をつくってみせている。こんなやり方を、加藤は
ひとつの「痛み」をともなうものであるとみる。そのうえで、これは、「作者」と「テクスト」の機能を
完全に分離させてしまうだけのポストモダン的言説では説明しきれないものととらえ直してみせる。
加藤は、水村自身がかつて自作をポストモダン的なものと説明していたことの矛盾を今になって
指摘している。 水村自身が、自分の創作の方法をどのように意識していたかは今となっては
かんたんにはいえないが、結局、問題は、私たちがほんとうに自己言及しようとすれば、自分が
つくったドラマの只中にいきなり放りこまれてしまう・・・ということなのであろう。 そして、この
「永遠のテーマ」を、いつも実にさりげなく、それでいて真正面から抱え込んでいるのが、
「岩松ドラマ」の登場人物たちであると私は思うのである。)

舞台『シブヤから遠く離れて』の登場人物たちは、シブヤの片隅から世界をただぼんやり眺めている、
眺めるしかない。「作者」と「テクスト」は、一度は切り離された。それでも、なお、岩松の舞台には、
いつも「作者岩松」がかたちをもたない「幻」のように舞台に現れてくるようにみえるのである。実際、
岩松作品には岩松自身が役者としてすこしだけ出演することが多い。が、『シブヤから〜』のように
役者岩松が登場しない舞台にも、「作者岩松」の亡霊的パワーはある。そして、この作品自体が、
青年と女とふしぎな亡霊のおはなしなのでもある。
二宮和也演じる青年が、渋谷の住宅地にある一軒の荒れ果てた家を訪れる。かつて友人とその母が
住んでいた家である。なつかしさに浸っていると、ふいに友人が現れる。そういえば、今日は友人の
誕生日だった・・・と青年は思い出し、友人といろいろ語りはじめる。でも、彼が語りかけている友人は、
本当は「幻」。家のなかには今、美しくも あやしげな女が住んでいる。小泉今日子演じるその女は、
ウェルテルという名の小鳥といっしょに、世界から身を隠すようにそこで暮らしている。青年と女、この二人
を癒すことができるのは、今はおもいでだけ・・・。ふしぎにひかれあっていく二人を、現実が襲う。女の
周囲を、ヤクザがらみの事件がとりまく。ゆめともうつつともつかぬ時間のなかで、青年は友人の幻と
語り合いながら、実は自分が過去に友人を死に至らしめた記憶にはげしく責められていく。そして、
女が、撃たれる。青年は少年のように頭を抱えて泣きくずれる。
「成長止めたかっただけじゃないか・・・!」
岩松作品を、岩松以外の演出家が手がける舞台は、おもしろいのである。昨年の『西へゆく女』には、
ケラリーノ・サンドロヴィッチ演出と岩松演出の2つのヴァージョンがあった。岩松とケラは、
「神経症っぽさ」(?)でどこかつながっているみたいでもある。だからこそ、逆に、ケラの演出と
岩松自身の演出は、互いにポジとネガのカラーをみせていたという感覚があった。ケラは、岩松テクスト
から立ちのぼる像だけから作られたもう一つの世界を再構成して舞台にのせる。このとき、
ある種の詩(ポエジー)が、私の目をとらえる。
『シブヤから遠く離れて』を演出する蜷川幸雄は、岩松のテクストをギリシャ劇、シェイクスピア劇、
または近松なんかの場合と基本的に同じように扱っているように思える。岩松のテクストからゆげの
ように立ちのぼる記号の多様性を、蜷川は蜷川ヴィジョンのなかに完全に密封する。演出家は、
いってみれば目のストーリーテラーともいえる。岩松が書いたピストルが「(物語のなかの)ただの
ピストル」であるとすれば、蜷川世界のなかでそれは、「完全な(物語のなかの)ピストル」に姿を
変えるのである。
私ははじめ、正直なところ、蜷川ヴィジョンと岩松テクストはぴったりとはいえないのではないかと
感じた。すべてのドラマのなかの感情は普遍的なものとも考えられるけれど、それをみせるスタイルは
いろいろあるのだと思う。 だから、ギリシャ劇もシェイクスピアも近松も現代劇もみんな同じような
蜷川式ヴイジョンにとじ込めてしまうのは、 ちょっともったいないような気がした。(舞台一面にたてものの
側面をみせるセット、おおきな花を林立させる美術、主役二人がスポットライトのなかで愛を語る場面
などに、やや既視感&違和感。)
しかし、しばらくして、考えた。岩松テクストをめぐって、今年のこの蜷川演出と昨年のあのケラ演出
とでは、どちらが「実験的」であったかといえば、むしろそれは今年の蜷川演出のほうといえるのでは
ないだろうか。それぞれにパワーをもちながら、一見ちょっと異質で合わないような演出家と作家が
肩をくんでつくった舞台は、意外にも岩松テクストの大切なポイントを私たちに上手に伝えていた・・・
今は私はそう思う。
岩松了の作品のなかで、「作者」と「テクスト」は、実はずっといっしょにいる。「テクスト」が
かろやかなことばの衣をまとうとき、「作者」と「テクスト」はお互いにまったく無関係のような
表情をすることもある。でも、『ワニを〜』の「きもちわるさ」も、『シブヤから〜』の「ゆめとうつつの
切れ目なさ」も、結局は同じひとつのことを示しているように私には感じられる。それは、私たちは
みな自分からどうしても「切り離せないもの」をもっている──だから、ピストルはあってもなくても、
私たちにドラマは起こる──ということである。
となると、『シブヤから〜』の舞台は、岩松の「想い」が、蜷川の「普遍性」にのせられて、
結果的に演劇と世界を切り離さずに重層的につなげていくひとつのおおきな試みになっていたと
いえるのではないだろうか。