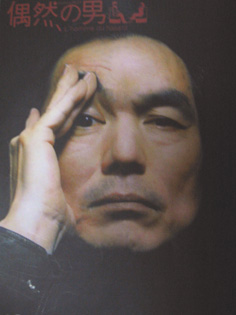
2004年7月 『偶然の男』
作 ヤスミナ・レザ
共訳 小田島恒志
大磯仁志
演出 鈴木勝秀
於 スフィアメックス
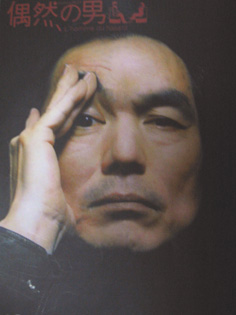
がらんとした舞台の下手に男がひとり、上手に女がひとり現れる。すぐに、暗転。再びライトが
つくと、舞台のまんなかにあるシートに向き合って座っているのは、二体の白いつるつるの人形。
人間は、あいかわらず舞台の両端に、なんだかさえない顔で佇んでいる。人形は、なにもしゃべ
らない。しゃべらないものが、しゃべるものをおしのけるように、芝居の舞台の中心におかれて
いる。そうすると、しゃべらないものも、しゃべるものも、かなしく、おかしく、まぶしくみえて
ドキドキする。
男性のほうが、やがてため息まじりに口を開く。彼は、ポール・パルスキー。初老の作家。
そこは、どうやらパリからフランクフルトへ行く列車のコンパーチメントの中らしい。といっても、
彼のことばは、よくあるように、私たちに舞台上のシチュエーションを解説してくれるわけ
ではない。彼は、今ここにいるだれかに語りかけているのではなく、ただ、ひとりで思考
しているだけ。たとえば、自分のこれまでの作品について、友人について、頭のなかで
もくもくと思いをめぐらせているだけ。そのうち、ささやかな人生をめぐる憤懣やら後悔やら
が胸の内にこみあげてくる。それというのも、彼のひとり娘は、もうじきみょうな男と結婚
しようとしているためなのである。結婚相手は、自分とほとんど年のちがわない、「小声で
ぼそぼそ話す男」らしい。
女性も、語る。彼女は、マルタ。はじめは楚々として冷静にみえた彼女が、興奮状態で
ぶんぶん語る。なぜって実は、彼女、作家ポール・パルスキーの超熱烈な愛読者なので
ある。そのパルスキーと、今自分がたまたま乗った列車の中で向き合って座っていると
いう事実に、彼女は完全にパニック状態。パルスキーの小説こそ、これまでの彼女の
人生をかたちづくってきたもの。彼女は、しばらくしてから、パルスキーの最新作『偶然の男』
をおもむろに膝の上にひらいてみせる。彼が、チラッとでもじぶんのほうをみてくれたら
とこころのなかで祈るきもちで。ただし、当人と客席の私たち以外の人間からみれば、
彼女の態度はいたっておちついてみえることを忘れてはいけない。彼女の魅力的な
おしゃべりもまた、自分のなかだけで行われている自己内部対話、つまりひとりごと。
現実には、彼女はそこに作家がいることになどぜんぜん気づいていないかのように
ふるまっているはずなのである。
彼女は、結婚も恋も子育てもそれなりによく経験してきている。亡くなった夫は、
パルスキーの小説に出てくる男にそっくりだった。二人の恋人のこと、変わった兄のこと、
そして、なにより、どれだけパルスキーに心酔しているかということ・・・彼女は、
"しゃべらず"にはいられない。そのことばは、つくられた物語のなかのセリフよりも
しなやかに、客席の私のむねに入り込んでくる。エビアンやポテトチップスを口に放り込み
ながら、夢中になってことばをさがしている彼女に、すごく親しみを感じてしまう。作家は
作家のほうで、とにかく人生にうんざりしたような表情を面にはりつけているものの、
目の前の彼女に、なにかあたらしい世界のはじまりを予感するだけのやわらかな精神を
もっている。二人とも、身のまわりにじぶんだけの小さな時間のかけらをたくさんくっつけて
いる、そんなタイプの人間である。突然色鮮やかになるおもいでや、少々やっかいな日常や、
ちょっとした未来なんかが、光のなかを舞う埃の渦のように二人のまわりを回りつづけて
いる。だから、二人は、しゃべりつづける。ひとりっきりで。いや、たぶん、きっとやってくる
にちがいない、ことばが絶える一瞬の、その先にいるだれかに向けて。

劇作家ヤスミナ・ レザが、登場人物に語らせることは、たいていごく日常的なことで
ある。家族・恋愛・ 仕事・・・をめぐるちょっとしたエピソード的なことを、ときにはおもしろ
おかしく、ときにはするどい批評精神をもって、かなり饒舌に語らせる。ならば、それは
いわゆるよくある「大人のウェルメイド風」かというと、ちがうのである。私が、レザの舞台
にものすごくひきつけられるのは、たぶん、その舞台のことばが、「見える」というより、
「ちゃんと聴こえる」ことばだからなのだと思う。それは、「ことば」として「聴こえる」だけ
ではない。それは、私の耳に、たしかに「音楽(音)」としてとびこんでくる。
ことばは、特定の生命ある人間どうしのあいだで意味をもつものと考えられる。言う
までもなく、 意味は私たちの外がわにもともとあるのではなく、私たちの内がわに
コミュニケーションをとおして生まれてくる。したがって、私たちのふだんのコミュニ
ケーションは、「言語的領域」にあるといえる。では、舞台と客席のあいだのコミュニ
ケーションは、どうだろうか?舞台上で語られることばというものは、やはり、私たちの
ふだんのコミュニケーションをふくむような「言語的領域」とは、またちがったおおきな
時空にただようものと、私は感じている。私が舞台のことばに、音楽のような響きを
求めるのはそのためだろう。舞台は人間にとってメタレベルにあるからこそ、演劇という
システムは機能するのだと考えられる。そして、そのことを、劇作家レザはよくわかって
いる。わかっていて、この作品のパルスキーやマルタや他の作品の中のいろいろな
人物たちには、身の回りのちいさなことを一見おおげさでないように語らせている、
そこがなんともかっこいい。(以前、日本で2回公演された『アート』は、一枚の抽象絵画を
めぐって3人の男がとにかくしゃべる舞台。レザの戯曲のことばは、「アート論」から
はじまって、いつしか私たちの感情によりそっている。)

ヤスミナ・レザ
とくに、この『偶然の男』にいたっては、たった二人だけの登場人物が、舞台のほとんど
の時間、顔を見合わせることもなく、それぞれが自分だけの「ひとりごと」を言っている
という構成になっているのである。つまり、これは、ある見方からすれば、ほとんど
なにも起こらない、おもしろくない舞台ともいえる。また、ある見方からすれば、ドラマが
ドラマを否定しているような矛盾からスタートしている舞台ともいえる。ところが、私は、
この舞台こそ、ややおおげさな言い方をすれば、実は今までみた舞台の中で、もっとも
美しく深いことばでみたされた舞台といってもいいような気が、今はしているのである。
ふつう二人の人物が出てくる芝居といえば、漫才のように丁丁発止とことばを交し合う
ものも当然あって、それはそれで、すばらしものであることも多い。ただ、そういう
ダイアローグをみせる舞台では、舞台のメタ性が認識されたうえで、客席に対して
「コミュニケーション」という要素が解釈のためのツールとして具体的に用意されて
いるといえるのだろう。これに対して、モノローグをみせる舞台には、すべての観客の
ための解釈のツールというものは、ほんとうは存在しないといえるのではないだろうか。
いいかえれば、モノローグということばは、客席というひとつのからだに作用するという
よりは、そのからだを構成する細胞のひとつひとつ、つまり観客ひとりひとりの「こころ」に
作用する、そんなことばなのかもしれない。この場合、舞台と、観客ひとりひとりは、
それぞれはじめは「閉じている」システムと理解される。といっても、多くのモノローグ
タイプの芝居と観客のカンケイが、決して閉塞的なものにはならないのはなぜだろう。
そう考えるとき、私は思い出す。そう、ひとの「こころ」そのものこそ、ときに、ひとの
存在のメタレベルにあるものなのである。
「ある人物が社会のなかで継続的に記述を生みだしているとき、その心は、
コミュニケーションを再帰的に産出している社会システムの拘束・制約のもとで
作動していると考えることができる。」(西垣通『基礎情報学』)
今、仮に、この文の、「社会」を「観劇」とおきかえてみると、ちょっとおもしろい。客席で
舞台をみているとき、私たちは意識するとしないとにかかわらず、なんらかのかたちで
こころを自動的にはたらかせているといえる。舞台から発信される情報を、自分なりに
解釈する作業を、こころは行なっている。いってみれば、こころは、いつもちいさなメモを
とっている、そんなところであろうか。(実際、私は観劇中にハッと気づいたことなどを、
暗い客席で思わずササッとメモしてしまうこともあるのだが・・・。)そもそも、「舞台」も
「社会」も、ひとのこころのさらに高次のメタレベルにあるものとすれぱ、たしかに、
観劇中の私たちは、舞台との「再帰的なコミュニケーション」の循環に入ることで、
一定の精神的拘束をうけているともとらえられると思う。ただし、大切なのは、「舞台」は
「社会」とはちがう、ということである。私たちは、社会のさまざまな場面で、他者との
拘束的なカンケイを経験しなければならないといえる。でも、ときには、自分とはとおいところ
にあったはずのひとつの社会のなかで、いつのまにか自由に他者と交流していると感じる
こともある。逆に、私たちがわざわざ劇場に足を運ぶということは、舞台からある種の
精神的拘束をあえて自分から受けにいくようなことなのかもしれない。すくなくとも私に
とって、舞台の拘束は、社会の拘束よりはよいものである。それでも、舞台をみながら、
予想に反して、作品世界と自分とのあいだにふしぎに自然な相互理解の感覚をもつ
とき、私はとてもしあわせな観劇をしているといえるのである。
ヤスミナ・レザの『偶然の男』にかんして言えば、それはとてもしあわせな観劇に
なった。もちろん、レザの書くながいモノローグのおかげである。そして、みじかい
ダイアローグのおかげである。私は、パルスキーとマルタの二人によってつむぎ
だされるモノローグについて、困難な解釈といえるような作業を行った記憶がほとんど
ない。そして、当のパルスキーとマルタ自体も、また互いに相手の言うことを解釈しよう
と奮闘するようなことはないのである。二人は、舞台のさいごに、ほんのすこしのあいだ
だけことばを交わす。だいたい、こんなふうに・・・。(ここで、やっと、舞台中央を陣どって
いた二体のつるつる人形は人間に席をゆずる。)
「ぼくは、不幸を書くことができないんだ。ボルヘスは、ブエノスアイレスで、あらゆる
ものに涙する男を書いたけど、ぼくにはできない。」
「そんなことありません!・・・あなたは全体を書いています。あなたの小説に出て
くる、いつもドレスアップしてひとりでランチをとる太った女性は、善良そのもの
なんです!」
出会ったばかりのパルスキーとマルタのこころが、はじめからジワッと溶け合っている。
ドラマとは、もしかすると、人と人との解釈合戦のようなものかもしれないと私は思う。
とすれば、そんな合戦はいっさい省いてすてきに成立しているこのドラマは、ドラマの
ちょっと前のドラマ?あるいはドラマのちょっと先のドラマ・・・?たぶん、両方である。
もっとも、パルスキーとマルタは二人とも、自分で自分を解釈するのにたいへんいっしょう
けんめいなタイプの人物ともいえる。だからこそ、私たちも、この舞台をみて、空を
見上げるように自分の「こころ」を自分でちょっとだけたかくもちあげて、光にかざして
眺めてみたい・・・そんなきもちになってしまうのだろう。


キムラ緑子 長塚京三
私たちの現実のなかにも夢のなかにも必ず、なんだかいきなりピンときて、ジワッと
くるポイントというものがある。そんなふしぎでリアルなポイントを、モノローグの環境に
すくいあげたこの舞台を支えるのは、なんといっても二人の俳優。作家パルスキーを
長塚京三、愛読者マルタをキムラ緑子が演じる。キムラは、持ち前の、ひとをたのしい
気分にさせるような雰囲気をふりまいて、たくさんのことばをパワフルに発する。いつも
書物をとおして自分を見つめながら、ときには奔放な想念を上手に操るマルタという
すてきな女性を、ぴったりに演じている。そして、パルスキーの長塚が、舞台のさいごに
マルタとうれしい会話をしながらみせるジワッの表情。この表情が、このドラマをなんにも
起きないドラマだなんて、だれにも決して言わせないのである。基礎情報学は、
「ひとりの人間が感じる痛みは他のだれにも分からない」と言う。たしかに、そうであるかも
しれない。けれど、ヤスミナ・レザの書く繊細な世界のなかでは、俳優長塚の「ひとりごと」
の一言一言が、人生の痛みそのものを強力に包み込む、まるで「痛みのためのメディア」
になっている。