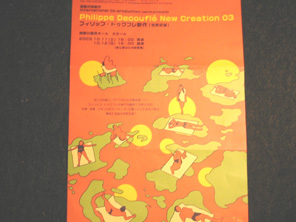
『IRIS』
フィリップ・ドゥクフレ 於 神奈川県民ホール
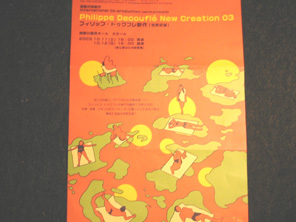
![]()
フィリップ・ドゥクフレの『IRIS』は、むかしなつかしい日本の紙芝居風にはじまる。それは、
だれかの思い出、それもネジの狂ってしまった思い出を覗いているみたいでもある。
青い目の「ハダカの大将」みたいなひと、まっ赤なながーい衣装の中国人、うすむらさきの
パンツの小柄な東洋女性、そんなちょっとおかしな三人組が、障子のむこうからパッとびだし
てくる。「わたくし、ゆうべはゆっくりおふろに入ったんですよ。あついおふろに入ってから
休むと、あたたかくってほんっとによく眠れるんですよ。そして、いいゆめがみられるんです
よ。・・・」そんなようなことをぺらぺらしゃべる。おしゃべりには、だんだん中国語、フランス語も
交ざってきて、ことばはリズミカルにつながっていく。ダンスと詩のコラボレーションはよくある
けれど、こういう語りのような、おしゃべりのようなことばとダンスの組み合わせをみるのは、
もしかするとはじめてかもしれない。もともと、ダンスはからだによる詩であるといえるだろう。
でも、こんなダンスとおしゃべりの共演って、舞台芸術のレベルでもっと可能性があるもの
かもしれない。
影絵の大小のウルトラマンみたいなもののたたかい、両手に剣をもってとびはねる中国の
舞、女を箸でたべようとする男の踊り・・・奇妙な「ダンス」がぞくぞく登場してくる。(「珍しい
キノコ舞踏団」の感じあり)そのあいだ、舞台上手の日本家屋に似たもののなかでは、
坊主刈りでランニングシャツに半ズボン姿のフランス人が、「わが家は、いいなぁ~」なんて
のんびりした調子の日本語で言っていたりする。そして、舞台下手には、ずっとフランス人の
女性歌手がいる。彼女は、舞台の時間をとおして、さまざまな声を響かせて、さまざまな
種類の唄を唄う。(沖縄の唄も、唄われる。)
「どのように日本人と中国人とフランス人がいっしょに交流し、行動し、空間を理解する
のか」─このテーマに沿って、ドゥクフレは、二年前から実際に日本と中国とフランスを
行き来してオーディションをくり返している。最終的に日本での二ヶ月ほどのリハーサルを
経てこの舞台をつくり上げた。日本人と中国人とフランス人、これらの異なった三つのものを
ひとつの舞台上にのせてみせるために、まず彼は、「家」(セット)と「音楽」(ライヴ)もいっしょ
に舞台上にのせてしまうことにするのである。「家」は、日常を詩的に表現するもの、と彼は
言う。リアルタイムで耳にとび込んでくる歌声は、観客の想像を十分にふくらませる。つまり、
ダンスの空間に演劇的空間をダイナミックに挿入するということでもある。異なった三つの
ものをなんとかつなげようとして、ドゥクフレはすてきにつなげてしまう。ドゥクフレ流
「つなげるマホウ」が光る。
「コンセプトに興味はない。すべては、コンセプトの奥にあるかたちからはじまる。」ドゥクフレ
は、こう断言している。彼は、「観客にメッセージを伝えているのではない」。この舞台を
とおして、「異文化交流はよいことだ」というようなお決まりの価値観を彼は示しているわけ
じゃないことはよくわかる。それよりも、もっと抽象的な、「視る」ことを通した「異文化交流の
スピリット」みたいなものを舞台にのせているのである。といっても、舞台芸術は、視覚的な
コンセプトなしに成立するものではない。舞台上のダンス(肉体)、装置、衣装、照明・・・etc.
は、それぞれに私たちが読み解くべきなんらかの概念的なメッセージを視覚的に伝えている
ことになる。そうした小さなメッセージたちを、ドゥクフレの「つなげるマホウ」が大きくつなげて
いく。観客としての私は、その「マホウ」がおもしろくて仕方ない。
ドゥクフレは、今彼がすきなこと・やりたいことをただ全部舞台にのせてしまっただけじゃ
ないかしら・・・一瞬そんなふうにも思える。でも、それにしても、彼は、どうやって、たくさん
の小さなメッセージとまったく非概念的な要素に統一を与えていくのだろうか。これには、
なにかやり方があるにちがいない・・・。なんていうことは、まぁ、あたりまえのようなことでも
あるけれど・・・、そんなあたりまえのようなことに、舞台をみる観客はハッとする。そもそも
舞台は、たとえそれがどんなにわかりやすい舞台であろうとなかろうと、やっぱり私たちの
現実からは遠い。舞台は、私たちにとって「異世界」であるからこそおもしろいのだから。
(ドゥクフレは自分が選択したメンバーに多くの振り付けをまかせている。「つなげるマホウ」
のヒミツは「ひと」ということだろうか?)
ところで、すばらしい「異世界体験」とは何だろう?『ファンタジーの魔法空間』(井辻朱美
著)によると、それは、自分の空間に他者の空間が侵入してくる危険なく、現実には視ること
のできない遠い時間を、近くでまるごと視る体験であるとも考えられる。といっても、この考え
は、現実に生きている他者を否定するような思想のレベルのものとはちがう。井辻は、人間
や生物には、もともとある種の「空間体験機能」とも呼べるものが内在しているのではないか
と考えている。だからこそ、人間がこれまでに書き記してきたファンタジー的なさまざまな
「異世界体験」の物語は、決して現実ではないけれど、たしかに真実であるといえるのだろう。
本来なら、自分の身(目)を痛めつけずに存在することのできない時空に、安全に足を
踏みいれることができる──こうしたパースペクティヴを得る感覚はひとつの「崇高さ」と
いうはるかな感覚にもつうじていく。ところが、そんなはるかさへ向かう素質は、特定の人間
にだけ備わっているというわけではない。物質レベルでの身体を超越した視線をもつ
可能性は、実は私たちひとりひとりの内にある。大切なことは、身体を超越した視線こそ、
「身体のセンサー」で語られるということなのだろう。「超越的視線」と「物質的身体」、この
二つはいつも微妙に繊細にかかわりあっている。(ちょうど「他者」と「自己」のように。)舞台
という「異世界」に向き合うときも、まずはこの二つの「かかわり」を自分なりにつかもうとして
いくと、たのしい。ドゥクフレのつくるステージは、まさにこのたのしさをたいへんわかりやすく
私たちに示している。コンセプトというよりはゆるやかなパースペクティヴをもつ術、つまり
「超越的視線」と「物質的身体」を「つなげる視線」をもつ術を「マホウ」と呼ぶなら、ドゥクフレ
世界はたしかにひとつの「マホウ空間」であるといえるのである。
人間同士がつながっていくことについて考えるひとつのアイテムとして、ドゥクフレは
「内臓」に注目している。たしかに、この舞台には、人間の内臓をイメージさせるオブジェや
動きが多くみられる。でも、実は、私は「内臓」のことはあまり気にせず舞台をみていたように
思う。私には、「内臓」も単なるひとつのコンセプトであるように思えるからなのかもしれない。
「コンセプトの奥のかたち」を大切に表現するためには、もしかすると「肉体」よりも「音楽」や
「ことば」だけのほうが向いているのではないだろうか・・・もともと文学志向でもある私は
そんなふうに思ってしまうこともある。特に西欧的思考からなる舞台で、「内臓」が意識されて
いたとしても、それがほんとうに「コンセプトの奥のかたち」を表現していると実感できるもの
とは限らない。肉体をとおした表現のなかでも、日本のブトーと比べれば、ドゥクフレ世界だって
むしろコンセプトだらけにみえてしまう。そして、私がドゥクフレの舞台ですきなところは、
東洋人の私からみて、「コンセプトをさけるというコンセプト」がしっかりみえるというところ
なのである。
もっとも、実際に、ドゥクフレがこの舞台のいちばん大きなポイントと考えているものは、
「内臓」よりもやはり「視野」のほうではないかと思う。たとえば、舞台一面に、なんのへんてつ
もない日本の街角の映像が映しだされる。スクリーンのなかで、ひとりの男が電柱にぶつかる。
そのとき、舞台上では、ひとりのダンサーがもうひとりのダンサーにごつんとぶつかる。観客
の日常をそのまますくいとってみせる映像のなかの動きと、日常から肉体だけをとりだした
舞台上の動きが、同時並行的にぴったりシンクロナイズしている。背景は、いつしか街角から
図書館になっていたかと思うと急にだれかの浴室らしきところとなって、舞台の視線は私たちの
生活のなかにぐっと深く差し込んできたりもする。よく見ていると、舞台上では、三人が三回
おなじことをしている。そして、スクリーンには、おなじ時間に三人の視野に入ってくるちがった
光景が順に映されているとわかる。つまり、観客は、一つの出来事をめぐる三つの見方を
見ることになる。私たちは、今じぶんがいっしょにいる相手の目には、世界はどんなふうに
映っているのかをこの目で見てみたいと思うことがある。そんな思いが舞台全体に展開されて
いく。
数年前、「視野交換装置」なるものを使った現代美術の観客参加型作品をTVでみた。この
「装置」を装着した二人の人間が、お互いに相手の目に映る光景をみながら動くことができる
というものだったと思う。けれど、視野を交換するおもしろさは当人たちにしかわからないの
だから、その作品のよろこびは、ちょっとヒミツめいているなと思った。ドゥクフレは、舞台という
空間で、視野交換の世界を多くの人々がいっぺんにたのしく共有できるようにしている。
こうして、ドゥフクレは、映像とダンスをたいへん大胆におもしろく組み合わせてみせているが、
そのこと自体は、今それほど私のこころをとらえない。それより、舞台いっぱいにあふれている
小さな「アソビゴコロ」や生演奏される曲の選択にうれしくなる。そして、ドゥクフレの「マホウ」の
仕掛けをちょっと探してみたくなる。
ドゥクフレが語ることをきいていると、どうやら彼の舞台づくりは、大きく分けて二つの局面から
はじまっているように思われる。つまり、技術的な局面と教育的な局面の二つである。彼は、
舞台上のひとつの展開を構成するとき、まずそれがメカニカルなテクニックのレベルでどのよう
に可能かを考えていく。映像を駆使するタイプの彼の舞台は、「人間が考えること」と「機械が
できること」がつねに絡み合ってできていくのだろう。人間のコンセプトを超えた世界とはどんな
ものか、いつだってはじめは彼にでさえわからない。だから、創作者の彼は、だれにもわからない
はずの世界を現実のことばで語り直す未知の言語の翻訳者にもなるといったところだろうか。
それと同時に、彼は、今はっきりわかっていることを未来に伝える仕事もしてきている。ドゥクフ
レは、はじめ、ダンスだけにとりくんできたダンサー独特の身体性と、映像だけをつくってきた
映像作家のコンセプトとは、どうしても合わないと感じたという。彼は、ダンサーの動きを
ほんとうに理解できる映像作家が必要と確信する。そして、ダンスと映像づくり、この両方に
ついて身をもって知り、それらをよくこなすことのできるメンバーを自分で育てることにしたので
ある。このために、彼はワークショップの活動を二十年つづけている。そう聞くと、私は納得も
するけれど、それでいて、正直なところなんだか疲れてしまうみたいでもある。「コンセプトの
奥のかたち」を表現するということ、これはなかなか時間がかかることなのであるなーと思う。
もしかすると、演出家が「マホウ空間」をみせるということは、『W文学の世紀へ─境界を
越える日本語文学』(沼野充義著)でとり上げられている「亡命作家の手法」にも似ている
かもしれない。現状にあってはひび割れた世界観のなかにしか生きられない作家は、自分の
個人的な状況からぬけ出して今までにだれもみたことのないような新しい文体を打ち出して
いくことを自ら選びとる。これを、「手法としての亡命」とよぶとすれば、ながい年月をかけて
現状を変えていこうとしてきたドゥクフレの舞台の手法にも、「亡命」的要素があるといえるの
ではないだろうか。それは、「目の亡命」ともいえるものである。そして、彼は、自らそれを
選びとっている。
この舞台のタイトル「IRIS」は、ギリシャ神話の天地を結ぶ女神。宇宙的な時間の流れの
なかで、ひとつの世界ともうひとつの世界をつなごうとする、そんな演出家の思いが大きければ
大きいほど、その舞台はたくさんの小さなたのしいことでいっぱいになるのだろうか。舞台は
現実からは遠い。それでも、魅力的な舞台の時間は、私たちのとてもなにげない日常的な時間
の流れとも実はちゃんとつながっている。だから、その舞台の記憶は、劇場を出たあとにも
ずっとつづいていく私たちの思考といっしょにつねに変わりつづけ、生きつづける。観客は、
舞台をみるだけでなく、当然日常を生きている。そんな「生きている観客」と「ひとつの舞台」を
つなぐ力も、やはり「マホウ」と呼べるだろう。 この「マホウ」を、私はちょっと「セカイシセン」
なんて呼んでみる。「セカイシセン」は、わかりやすい。「セカイシセン」は、今世界中のさまざな
年齢のさまざまな状況にあるひとびとのための舞台をつくる。そして、その舞台にのせられる
ものは、自然に多くのひとが自分なりにみたり・きいたり・おしゃべりしたりするための良質な
素材ばかりである。なぜかといえば、「セカイシセン」とは、舞台をつくるひとりの人間の、
世界に向ける「思い」の確かさのことだからである。
こんどの舞台のなかで、今とくにつよく私の印象にのこっているダンスのひとつに、
「七拍子のダンス」とよばれるものがある。舞台下手の女性歌手が、「1~7」までの
数字を唄うようにゆっくりカウント(フランス語)している。何人ものダンサーが両腕を
大きく回しながら、後ろ向きに舞台を横切ってゆく。こういうシンプルな振り付けをみると、
いつも私のきもちはパッとあかるくなるのである。ダンサーたちはそれぞれにいろいろな
方向をむいておなじ単純な動きをつづける。そのうち、舞台上に、ひとつの空気の流れ
だけが見えてくる。そして、ダンサーの腕が異様に長くみえる。そう思ったとき、私の胸に
たくさんのばらばらのことばがあふれてくる。私は、そのばらばらのことばを自分で
ムリにつなげようとはしない。けれど、舞台をみているあいだは、どのことばもほんとうは
みな自然につながっていて、意味をもっているのだと感じられる。あとできいたところに
よると、ここでドゥクフレは特殊なライトを使っていたらしい。そのため、ダンサーの腕の
動きの残像が、コマ送りのフィルムのように観客の目に映る仕掛けがしてあったのである。
でも、もちろん、こんなタネアカシ的なことは、ただの現実の舞台空間について説明
しているだけであると思う。ドゥクフレの「マホウ空間」のヒミツは決して解き明かされは
しない。というのも、彼の舞台をみる観客は、物質としての「舞台空間」だけではなく、そこには
とらえきれない、あるひとつの「思い」をそのまま体験することになるからなのだと考えられる。
どんな空間にもおきかえられない演出家の「思い」=セカイシセンは、演劇的な「状況」とも
呼べるものを舞台上に呼び込んでくる。それは、永遠に不可視のものであり、まったく知覚でき
ない。だからこそ、自分の胸の奥にたくさんのことばが奇跡のように生まれてくる瞬間、私は
同時にこう思う。ドゥクフレのいう「コンセプトの奥のかたち」って、それはやっぱり「詩」のこ
とだったのだ・・・。
![]()