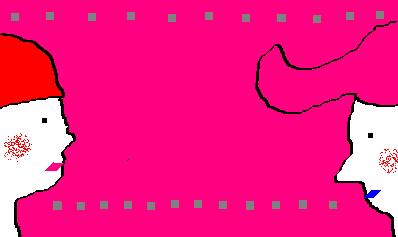
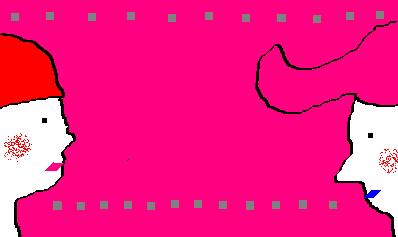
Ⅰ
窓口というものには
はじめはいつも猫が出てくる。
はじめの猫は
はじめの声を
のみこんでしまう。
どうして?
尋ねることができない。
こういうこと?
聞いてみることができない。
ただ
いつも
猫も私も
しずかにあしたを呼んでいる。
郵便局員は
5秒後にあわててやってくる。
どんなことばもひきよせぬまま
冷めたぬくもりを制服のあちこちにくっつけて
とんでくる。
冊子小包の
封筒の
右上の
ちょこんと切られたところから
世界をぐるぐるのぞきこむ。
実は
彼はのんびりしたひとである。
でも
なんでも早く
分かりたいひとでもある。
彼は
なんでも
早く
分かりたいひとである。
けれど
分からないないなら
分からないでもかまわない、
そんなひとでもあるかもしれない。
封筒をのぞいている彼に
どうして?
尋ねることはしない。
こういうこと?
聞いてみることはしない。
しかし
タッチ、
それは
封筒の外にある
ある一定の
ゆくりなく
たっぷりとした
きもちのひろがりである。
(メダマガ オッコチソウニナル マデ
ユメ ミテイマシタ。 )
寛大であることと明快であることは
やっぱり一致するわけがない
のだけれど、
ふたつの世界が
しばらくしずかに向き合って
おぼろのはるに
触れている。
にこにこ
ではなく
くすくす
触れている。
窓口というものには
はじめはいつも猫が出てくる。
|
Ⅱ 猫が映っているテレビジョンがあるのだった。 画面の中で
噛み千切られたような穴が
それにしても、
「あ!」
私のバッグをネズミはどんどん食べていく。
「あなたののんでいるそのミルクは、豆乳なのよ!」 私は
(アノヒトノ ココロダケ タダ ソレダケガ
ト オモッテイマシ タ。)
|
Ⅲ
ここは、公園である。
公園で、私はすこしウソをつく。
「初対面のひとが、いきなり自分の右目を私の左目にぴったり重ねてくる
ことが
よくある。このようにされると、私はどうしても一瞬両目をぎゅっと固くつぶってし
まう。でも、道を歩いていて、よく知らないひとの身が私の身に急にふわっと重なって
きたとしても、私はなかなかすぐには反応しない。何か特別な事情とか、とっさの理由
があるのかもしれないし、ないのかもしれないなどと考える。あくまでも全身と全身の
かかわりにおいてのことなら、私は大丈夫である。」
こんなことを私は言って
あとになって
「コレ、ウソ。」
と自分で気づく。
すいている電車の座席に座っている私のひざの上に
ごくふつうに座ってきたひとがいて
びっくりしたことがある。
私は公園で
すこしウソをつくことによって、
光之進(みつのしん)に軽侮の念を叩きつけられる。
けれどもこれも
すぐに思い過ごしであると分かる。
光之進のテントに
私はもぐる。
しめった手が、
肩に触れる。
カタノチカラってなんだろう・・・?
|
Ⅳ 今、
そう答えて、
郵便局員である
彼は
ときどき
そんなことをする彼を
そんなことをする彼を
|
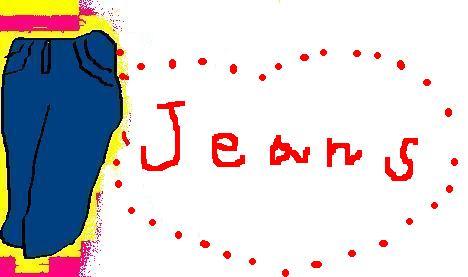
Ⅴ
もう、
テントは燃やしてしまうと
光之進が
言う。
ここは、公園である。
けれど
いつのまにか、
公園とは
名
ばかりといった感じの場所になっている。
かっこいい男女のみが集まってきて
ここは、今、ほとんど
モデル事務所である。
「このあそびちらかした匂いに、昏倒しそうだわ~ん!」
モデルのひとりがのけぞりながらつぶやく。
そのつぶやきが
まるで合図であったかのように、木陰からいつもの郵便局員がとびだしてきて、テントの
前に立っていた光之進にいきなりパッと挑みかかる。たちまち、ふたりは黒とオレンジの
二色のボールになってぶつかりあい、まざりあい、まったくひとつのかたまりになって、
モデル事務所の外の通りにころがっていく。アスファルトの表面にうっすらたまっていた
はるの陽射しが、黒とオレンジのマーブル模様のかたまりを迎えて輝くと、かたまりの中
にまぶしい山吹色が流れ込んでいく。黒とオレンジと山吹色の三色のマーブル模様に
なった、このよく弾むボールを追いかけて、こんどは私もころがっていく。気がつくと、
私は、生まれてはじめてアスファルトをはだしで踏んでいる。そう気づいたとたん、
ひとつの記憶みたいなものが私のあしのうらをくすぐりはじめる。そう、私は、むかし
歌手であった。だから、今だって歌手なのである。ということは、これから歌手になろうと
する必要はない。しかしながら、私が歌手であるとしても、それでも、私という生命全部
を、ときにバラバラにしようとするおそろしいものの正体はなんなのだろうか・・・?
それは、実は、たいへんよわいものであるらしいのである。